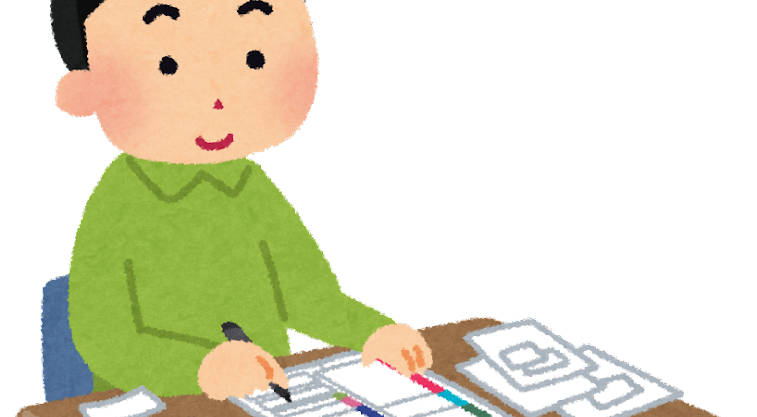今これをご覧になっている方は、今からドローン(無人航空機)学科試験の受験を考えている方でしょう。
学科試験は、試験機関での一発受験・講習機関で受講のどちらでも避けては通れない試験。
また、講習機関での学科講習だけでは、学科試験合格に不安!というお声もよく聞きます。
そこで、無人航空操縦者技能証明 学科試験の勉強方法についてお伝えします。
ドローン(無人航空機)学科試験の試験範囲について
まず初めに、試験範囲の確認をしましょう。
試験は、国土交通省が発行している教則本が基準となります。

講習機関の学科講習も、こちらの教則本を基準に講習を行っています。
試験には、二等と一等がありますが、多くの部分が重複しています。
【一等・二等共通試験範囲】
| 無人航空操縦者の心得
・操縦者の役割と責任 ・安全な飛行の確保 ・事故が起きた時の対応 無人航空機に関する規則 ・航空法全般 ・航空法以外の法令 無人航空機のシステム ・無人航空機の特徴 ・飛行原理と飛行性能 ・機体の構成 ・機体以外の要素技術 ・機体の整備・点検・保管・交換・廃棄 無人航空機の操縦者及び運行体制 ・操縦者の行動規範及び遵守事項 ・操縦者の求められる操縦知識 ・操縦者のパフォーマンス ・安全な運航のための意思決定体制(CRM等の理解) 運航上のリスク管理 ・運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案の基礎 ・気象の磯知識及び気象情報を基にしたリスク評価 ・機体の種類に応じた運航リスク評価及び最適な運航の計画の立案 ・飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航の計画の立案 |
【一等のみの試験範囲】
| ・無人航空機の飛行性能
・飛行性能の基本的な計算 ・カテゴリーⅢにおけるリスク評価 |
ざっくりいうと、一等のみの問題は、計算問題と、リスク評価の問題ということになります。
二等と一等の試験の違い
二等と一等に違いは・・試験の時間が、30分と75分で、一等が45分長くなります。
問題数は、50問と70問で一等が20問多くなります。
筆者は、どのような問題が出題されるか?情報収集のため、二等を受験後、一等を受験しました。
そして、分かったことは・・
共通範囲の問題は、全く同じ問題が出題されていたということです。

問題は、一等、二等それぞれ問題は数パターンあって、ランダムに出題されるという噂ですが、私の場合、たまたま同じパターンが被ったということなのでしょうが、一等試験を受けたときは、共通範囲の約50問(二等範囲)は全く同じでした。
では、残りの20問は、どのような問題か?というと
| ・計算問題 5問
・リスク評価の問題 10〜15問 ・その他、一等のみの範囲に関する3択問題 |
二等と一等の試験の難易度
二等試験は、30分で50問解く必要があります。
1問、約30秒・・と考えると、結構ハードだな・・と思い、受験しましたが、実際受けてみると、かなり時間は余りました。
私の場合、かなり準備(勉強)はしましたので、誰でも受かりますよ!という意味ではありません。
しっかり勉強しておけば、怖がることはない、ということです。
時間もかなりあまり、早々に受験会場を退出しましたが、同じような方はたくさんいらっしゃったと思います。
3択で出題されますが、そこまで判断に悩むものは少なく、きちんと法令など理解しておけば、回答できる問題です。
とはいえ、どのような試験も、スタート時期は易しく、徐々に難しくなったり、捻ってきたりしますので、受験を考えていらっしゃる方は、早めの受験をお勧めします。
では、一等のみの試験範囲についてですが、計算問題は必ずクリアしておきましょう。

国土交通省から、サンプル問題が出ていますが、やはり計算問題も表示されています。
私が受験した時に出た計算問題は、
| ・フレネルゾーンの計算
・飛行機の旋回半径(バンク角) ・水平到達距離 ・滑空距離 ・仕事率 |
などです。(受験経験者に聞いた情報も含む)
最低限上記については、解けるようにしておきましょう。
どれも、公式を覚えて数字をはめ込むだけですので、しっかり公式を覚えて、練習問題を繰り返しといて、機械的に解ける状態にしておきましょう。
次に、リスク評価についてですが、こちらの出題パターンは
「・・・・こういう状況で飛行させます。その場合にとるべき対応はどれでしょうか?」
というのが基本パターンです。
問題としては、それ以外の3択問題と違い、少々文章量が多く、一見難しそうに見えますが、しっかり状況をイメージすれば、何を問われているか?理解できます。
ここで、「しっかり読み込む」時間を確保するためにも、計算問題は、機械的に進めたいところです。そのためにも計算問題は、しっかり公式を覚えて、さくさく解けるようにしておきましょう。
さて、リスク評価問題ですが、こちらも法令や機能について理解できていれば、解けるはずです。特に、無人航空機に備えられている安全対策の機能については、どのような時に、どのような状況を避けるため(確保するため)の機能か?理解しておきましょう。
| ・フェールセーフ機能
・ジオフェンス機能 ・パラシュート |
など。
例えば・・無人航空機が墜落した際の被害軽減のための対策であれば、パラシュートを使用しますが、歩行者がいるので危険、その対策にパラシュートを使用するのは違いますね。
そのように、何をするために(何を防ぐために)どのような機能が効果的か?
そして今出題されている状況は、何を避けたいと問われているのか?
を考えると難しくありませんので、落ち着いて解いてください。
よって、こちらの難易度も、基本的な知識があれば、難しくはありません。
つまり、二等との共通箇所をしっかり勉強することが、リスク評価の問題にも役立つということになります。
私の場合、一等試験の時も時間は少し余りました。計算問題の見直しやリスク評価も見直し、それでも時間は余ったので早めに退出した・・という感じでした。

学科試験勉強法について
まず初めに、教則本をしっかり理解すること。
これが何よりの基本となります。
ただ、国土交通省の教則本だけでは、少し不足(簡易な説明)だけの箇所もあるので、理解できない時はインターネットなどで情報を探し、自分自身で理解できるまで調べることをお勧めします。
次に、私自身が効果的と感じたのは、本番同様の選択問題の模擬を繰り返し練習するとです。
今は、アプリで問題を作成したりできますので、ご自身で作成されてもいいでしょうし、昔ながらの単語カードも懐かしいですね。
そのようなものを活用しても効果的かと思います。
私は、仕事柄、得意分野でしたので、自分で選択式のイーラーニングを作成し、それで勉強しました。
本番は3択なので、4択にし、少し難易度を上げていました。
おかげで本番は非常に簡単に感じることができました。
知人にも試してもらって、かなり役に立ったと言ってもらいましたので、ここで販売することにしました。
もしよろしければ、使ってください。(1問ずつ解説をつけたので、それを読むことで自然と覚えました)
でも先ほど書きましたように、自分で作成しても、作成することも勉強の一環になるのでもちろんお勧めです。
私は、別の資格を取る時、アプリで作成し、通勤の際ずっとそれをやって、その資格も取得しています。
どんな資格も、勉強しやすい環境を作ることと思います。
「スマホを開ければ勉強できる」これは、電車、ベッドの中・・で大活躍するのでお勧めです。
「読む」も「解く」の繰り返しが合格へのコツです!!
何度も何度も繰り返し、試験会場の待合室まで諦めず「読む」「解く」すれば、必ず合格できると思います!
これから受験される方も、少しの時間も有効に使ってぜひ合格勝ち取ってくださいね!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
無人航空操縦士学科試験練習問題(eラーニング)があれば、通勤時間・寝る前の時間など有効活用して勉強ができます!
登録講習機関での実技・学科講師を勤め、自らも一等学科試験は一発合格!
自信を持ってお勧めする練習問題(過去問あり)です。
繰り返し学習できるので、効果的!
無人航空操縦士学科試験練習問題(eラーニング)のお申し込みはこちら!